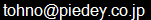|
||||||
|
もう40歳をとっくに過ぎたというのに。 今更、彼女にときめくとは思わなかった。 田望奈衣は、「たのぞみ・ない」という珍しい読み方をする名前だけで印象に残っていたわけではない。彼女は間違いなく魅力的な女性であり、かつ、男達の間に入っていって一緒に活動することにためらいはなかった。彼女は俺らのマドンナだった。 しかし、俺がもう40歳を過ぎているのに、田望奈衣が若いままということはあり得なかった。 街でばったり出会った田望奈衣は、既に若くはなかった。しかし、彼女は成熟した大人の魅力を身につけていた。しかも、まだ独身だった。熟女の魅力という奴が分かるようになってきた俺は、彼女から目が離せなくなった。 俺はその夜、彼女を誘って飲みに行った。 その結果、分かったことは、未だに彼女は熱烈な野球ファンだったということだ。特に彼女のお気に入りはプロ野球のナイターだったが、それは何ら変わってはいなかった。そして、それは父親譲りの趣味だった。父親は自らの趣味を名前に託して田望奈衣(たのぞみない)という名前を付けたのだ。つまり、姓名を逆転し、「望」を「のぞみ」と読まずに「棒」と読み、「ー」に置き換えると、「ないたー」になるわけだ。 田望奈衣自身がその事実を知ったのは、成人した後だったと言うが、その頃は既に大のプロ野球ナイターのファンだったので、思いがけないサプライズに喜んだという。 そこで、俺は彼女の口説き文句を考えた。そして、「俺が泣いた野球はナイター」という言葉を考えた。野球など見ない俺は野球の話で彼女に合わせられない。だから、せめて彼女の好きな話題のダジャレの1つも言おうとしたのだ。 だが、3回目のデートでそれを言うと、彼女は喜ばず、それどころか呆れた顔になった。 「それで口説いているつもり?」 「そ、そうだっ。悪かったな。だじゃれぐらいしか言えなくて」 「別にいいのよ。伴侶にまで野球の詳しい知識を求めてないから。ただ、好きという気持ちの本気は見せて欲しいわね」 「どうすればいいんだ?」 「私が愛読している『野球ばかマガジン』に、その言葉を掲載して見せて」 「ええっ!?」 「雑誌のライターをやっているなら、それぐらい本気を出せばできるでしょ?」 それは彼女の誤解だった。パソコン雑誌の技術系ライターが、スポーツ雑誌に書くつてなど持っているはずもなかった。 しかし、挑戦された以上は対応しなければならない。 俺は徹底的に野球のことを調べ、野球の試合を観戦し、ネット上に『ナイター大好きブログ』を開設して熱い文章を次々と掲載した。それを行っているうちに、野球の面白さが分かってきたので、熱意も倍増した。ネット上の有名野球ファンの仲間入りをするまで、それほど時間は掛からなかった。 その結果、野球の専門誌や広報誌からの執筆依頼も来るようになった。 俺はそれらの仕事をこなして実績を積んだ。 やがて、ついに待っていたものが来た。『野球ばかマガジン』からの原稿の依頼が来たのだ。 俺はこの原稿が掲載されますように、と祈りつつ『俺が泣いた野球はナイター』と題した記事を執筆した。 祈りは通じた。原稿は、編集者も編集長も大喜びの傑作と評価された。 電話を掛けてきた編集者は言った。 「素晴らしい原稿です。野球への愛が溢れんばかりです。来月号への掲載が決まりました。既に印刷の方にまわっていますから、店頭に並ぶのは間もなくですよ」 俺はそれを聞きながら心の中でガッツポーズを取った。記事『俺が泣いた野球はナイター』は、ナイター好きの田望奈衣さんへのアピール度は最高だろう。何しろ、田望奈衣という名前からして、ナイターのもじりなのだから。他の言葉では、絶対にこのインパクトは出ない。 そして編集者は、付け加えるように言った。 「そうそう。弊社の社内規定では、ナイターは和製英語の疑いがあるから使用しないことになっています。原稿は全てナイトゲームという言葉に置き換えられました。ご承知置きください」 (遠野秋彦・作 ©2008 TOHNO, Akihiko) |
|
||
|
|